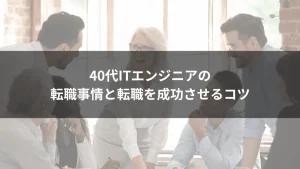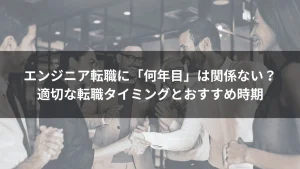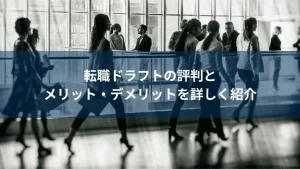「エンジニアとして1年の経験しかないけど、転職を考えている。自分の市場価値はどのくらい?短期離職ってやっぱりリスクなの?キャリアアップを成功させるにはどうすればいい?」
この記事では、そんな疑問にお答えします。
エンジニア採用担当の視点から、現場のリアルな事情と具体的なアドバイスをお届けします。
結論として、この記事のポイントは以下です。
- エンジニア実務経験1年でも転職することは十分可能。
- キャリアアップにつながる転職もあれば、そうでない場合もある。いくつかのポイントを抑えることが重要。
- 短期離職を繰り返すと市場価値が低下する可能性がある。ブラック企業を回避する対策は不可欠。
この記事では、エンジニア経験1年程度の方が転職を考える際に押さえておきたいポイントを具体的に解説していきます。
実務経験1年でも市場価値はあるのか?転職できるのか?
1年経験でも転職は可能。ジュニア枠の採用が増えている
エンジニアとしての実務経験が1年しかない場合でも、転職は十分に可能です。
近年、企業はエンジニア採用を強化しており、ジュニア枠や未経験者向けのポジションが増加しています。
たとえば、以下のような転職理由をお持ちの方も多いのではないでしょうか?
- 自社プロダクトの開発に携わりたい
- 上流工程からプロジェクトに関わりたい
- モダンな開発言語やフレームワークを使いたい
- 将来的にはマネジメントに挑戦したい
このような目標を叶えるためにも、自分のキャリアの方向性を明確にし、それに合った企業を見つけて転職活動することが重要です。
エンジニアは経験年数だけで評価されない
エンジニアとして評価される際、単に経験年数だけが基準になるわけではありません。
企業はスキルやその1年で何を成し遂げたかに注目します。
たとえば、筆者が採用支援をしているあるスタートアップ企業の採用担当者はこう語っています。
「チャレンジングな経験を持つ人を採用したい。経験年数は関係ない。」
ここで言う「チャレンジングな経験」の例としては、次のようなものが挙げられます。
- 自らサーバーを構築し、Webアプリケーションをリリースした
- 業務効率化ツールを自作して開発に活用した
- 新しいプログラミング言語を採用し、チーム全体が迅速にスキルを習得できる仕組みを構築した
これらの事例は一部に過ぎませんが、エンジニアは「成果」や「スキルの応用力」を重視される職種です。
経験年数よりも、どのようなプロジェクトに取り組み、どんな価値を提供してきたかをアピールすることが大切です。
実務経験1年の転職で実現できること
実務経験1年でも転職で環境を大きく変えることは可能です。
転職によってすぐに変化が期待できる主なポイントは以下です。
- 年収のアップ
- 新技術へのチャレンジ
- 業態の変化(事業会社、SES、受託開発など)
- 働き方の改善(リモートワークなど)
年収のアップ
年収はスキルに比例する要素が大きいものの、企業の給与水準が異なるだけでもアップが可能です。
特に、エンジニアが求められる現在の売り手市場では、候補者側が有利な立場を取ることができます。
「現年収よりアップ」を基本に転職活動を進め、希望年収を明確にしておき、面接時に即答できるよう準備することが大切です。
新しい技術へのチャレンジ
転職を通じて、新しい技術を使う環境に身を置くことができます。
例えば、AWSやGCPなどのクラウド環境、PythonやGoなど比較的モダンな言語を用いた開発ができる可能性もあります。
その一方で技術は日々進化しており、将来的に技術環も変わる可能性もあります。
従って、本来的には、採用している技術そのものではなく、その技術を採用した背景(技術選定に対する考え方)を知ることで入社後のギャップがなくなります。
業態の変化(事業会社、SES、受託開発など)
転職をきっかけに、業態を変えることも可能です。
たとえば、SES企業での実務経験1年から、事業会社へ転職するケースは珍しくありません。
よくある業態変更の例はこちらです。
- SES → 受託会社
- SES → 事業会社
- 受託会社 → 事業会社
- SIer → 事業会社
事業会社は人気ですが、多様なプロジェクトに携わることを目的に、あえて受託会社を選ぶ人もいます。
自分のキャリアプランを明確にして選択することが重要です。
働き方の改善(リモートワークなど)
リモートの頻度など、働き方を変えることができます。
「好きな場所で働きたい(地方在住など)」、「子育てや介護のため、なるべく出社は避けたい」といった理由でリモートワークを希望する方は多いです。
その一方で、「自宅では集中しづらいので、定期的に出社したい」という理由で出社を希望する方もいます。
企業によって「完全リモート」「ハイブリッド」「完全出社」など働き方が異なるため、自分の希望に合う企業を選ぶことがポイントです。
実務経験1年程度で転職をする場合の注意点
転職は理想のキャリアに近づくチャンスですが、エンジニア経験1年程度の方はいくつか注意すべきポイントがあります。
- ブラック企業を回避する
- キャリアの方向性を明確にする
- 過去の経験がまったく活かせない転職は避ける
ブラック企業を回避する
次の会社ではブラック企業に入社しないことが重要です。
次の職場でも短期離職をしてしまうと、1年程度の短期勤務が2回続くことになり、採用側からの評価が低くなりかねません。
企業は基本的に、採用した社員に長く働いてほしいと考えています。
短期離職が続くと「またすぐ辞めてしまうのではないか」と懸念され、採用対象から外されるケースもあります。
たとえば、筆者が支援している企業の一つでは、20代後半で1年程度の短期離職が2回続いている場合、その時点で採用対象外とする方針をとっています。
これは、どれほどスキルが高くても「すぐに離職するリスク」を重視しているためです。
このような評価を避けるためにも、慎重に次の職場を選びましょう。
ブラック企業を回避するための10のチェックリスト
ブラック企業を避けるためには、事前のリサーチが欠かせません。このチェックリストを参考に、企業選びを進めましょう。
3つ以上「No」の場合は要警戒、5つ以上「No」でブラック企業の可能性が高いと考えられます。
ブラック企業を回避するための10のチェックリスト(ココをクリック)
- SNSやネット上に悪い口コミ・評判はありますか?
- 離職率・在籍年数の情報は開示されていますか?
- 残業代や休日出勤手当がきちんと支給されますか?
- 有給休暇やリフレッシュ休暇の取得率は高いですか?
- 給与・報酬体系が明確に説明されていますか?
- 評価制度に透明性はありますか?
- 技術やスキルアップを支援する制度はありますか?
- エンジニアの働く環境(開発環境・ツール・PCスペックなど)は整っていますか?
- 面接ややりとりのレスポンスは適切ですか?
- 面接時に「やたらと体育会系ノリ」や「根性論」ばかりを強調していませんか?
キャリアの方向性を明確にする
「なぜ転職をするのか?」「次の会社で何を身に着けたいのか?」といったキャリアの方向性を明確にしておくことは重要です。
エンジニアとしての経験がまだ浅い段階だからこそ、長期的なキャリアプランを描いておくと、転職後のミスマッチを防ぎやすくなります。
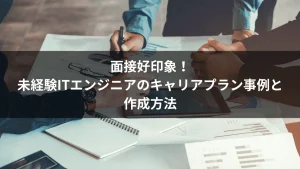
過去の経験がまったく活かせない転職は避けるべき
キャリアを積み重ねていくことは、長期的な成長において非常に重要です。
意図的にキャリアチェンジを行う場合は問題ありませんが、興味本位でこれまでの経験がまったく活かせない分野に転職することはおすすめしません。
例えば、バックエンド開発の経験があるにもかかわらず、スマホアプリエンジニアになる、インフラエンジニアになるといったケースが該当します。
もちろん、新しい領域に挑戦すること自体は悪いことではありません。
しかし、少なくとも「自分がこれまで身につけた経験をどのように転用できるか」「これまでのスキルセットを足掛かりにしてどんなキャリアが築けるか」をイメージできる道を選ぶほうが、転職活動を成功させる確率が高まり、キャリアアップにも繋がります。
転職活動を成功させるポイント
ここまでの内容を念頭において、早速転職活動をスタートさせましょう。
転職活動では、以下3つのポイントを抑えると転職活動がうまくいく確率が高まります。
- GithubやQiitaなどのアウトプットでスキルの高さを示す
- カンファレンスの参加や資格取得を通じて、高い成長意欲を示す
- 退職理由・転職理由を論理的に説明し、次の会社では長く働ける理由を説明する
GithubやQiitaなどのアウトプットでスキルの高さを示す
まず、経験年数が少ないため、ご自身のアウトプットによりスキルの高さをアピールすることが大切です。
実務経験の浅いエンジニアの場合、企業側からは「実力があるのかどうか判断しにくい」という見られ方をされることがあります。
そのため、実際に自分がどのようなコードを書いているのか、あるいはどのような技術的知見を持っているのかを客観的に示す材料として、ソースコードや技術記事を公開することが有効です。
GitHub上のリポジトリに加えて、Qiitaなどで学習内容やトラブルシューティングの過程を記事化しておけば、採用担当者や面接官が「この人はどんな観点でプログラムを組んでいるのか」「勉強への取り組み方はどうか」といった部分を把握しやすくなり、実際の経験値を示す説得力にもつながります。
カンファレンスへの参加や資格の取得を通じて、高い成長意欲を示す
次に、高い成長意欲を示すことも大切です。
定期的なカンファレンスへの参加や資格の取得など、学習・情報収集に積極的な姿勢を示しましょう。
「学び続ける人材」はどの企業にとっても将来性が高く、積極的に採用したいと考えられやすいため、資格学習への取り組みや学習実績を整理しておくとよいでしょう。
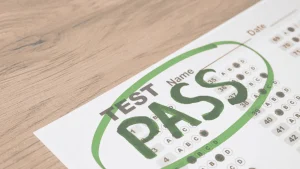
長く働ける理由を説明する
退職理由や転職理由を論理的に説明し、次の会社で長く働ける理由をきちんと示すことが重要です。
エンジニアとしてのキャリアが短い段階での転職だと、面接官は「またすぐ辞めるのではないか」という懸念を抱きやすいものです。
そこで、これまでの経験でどのような課題や不満を感じ、次の会社ではどのように解決したいのかを、具体的かつ論理的に伝えることが重要になります。
単に「もっとお給料が欲しい」「チームが合わなかった」という抽象的な理由だけではなく、「新しい技術に挑戦できる環境を求めている」「スキルアップするためにより大きなプロジェクトへ参画したい」といったように、次のステップを見据えたキャリアビジョンを分かりやすく話すことが大切です。
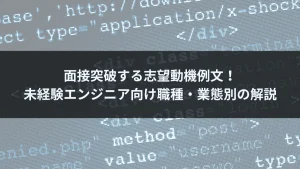
まとめ
エンジニア実務経験1年でも転職することは十分可能です。
その一方で、いくつか注意すべきポイントがあります。
- ブラック企業を回避する
- キャリアの方向性を明確にする
- 過去の経験がまったく活かせない転職は避ける
また、以下3つのポイントを抑えると転職活動を成功させる確率が高まります。
- GithubやQiitaなどのアウトプットでスキルの高さを示す
- カンファレンスへの参加や資格の取得を通じて、高い成長意欲を示す
- 退職理由・転職理由を論理的に説明し、次の会社では長く働ける理由を説明する
少しでも皆さんのお役になれば幸いです。